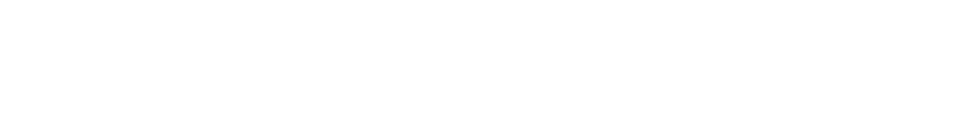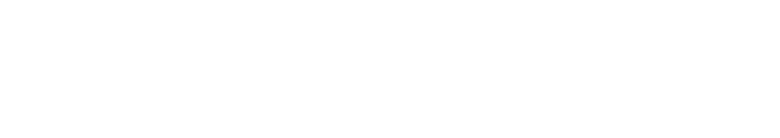配属希望の皆さんへ
研究室の見学について
2025年の研究室見学会は、11/27(木) 18:10と12/15(月) 18:10に開催します。
見学希望の3年生は、見学日3日前までにメールにて磯部へお知らせください。
研究テーマ「蛍光体」の紹介
当研究室では、発光する材料「蛍光体」を研究テーマにしています。蛍光体は、私たちの身近で利用されています。例えば、ディスプレイや照明は生活に不可欠です。さらに、太陽電池、セキュリティーなどの用途へ応用できる蛍光体もあります。
白色の光は、青色と黄色の光、または、青色(B)・緑色(G)・赤色(G)の光から作り出すことができます。青色発光ダイオード(LED)が開発されて以来、青色の光を吸収して黄色、緑色や赤色の光に変換する蛍光体が求められています。当研究室では、このような蛍光体としてYAG:Ce3+ナノ粒子を開発しました。現在、さらに量子ドット(Quantum dots; QD)とよばれる蛍光体の研究に力を入れています。新しい量子ドットディスプレイでは、広い表示色域を可能とする広色域ディスプレイが実現できることから、量子ドットは非常に注目されています。
蛍光灯のような従来の照明では、紫外線の光を可視光へ変換して白色の光が作られています。しかし、紫外線を可視光へ変換するよりも、青色の光を黄色、緑色や赤色の光に変換する方がエネルギーの損失が小さくなります。このため、省エネルギー化を進めるために、青色LEDと蛍光体を組み合わせた白色照明が急速に普及しています。
太陽電池は、すべての波長の太陽光を有効に活用できていません。たとえば、結晶シリコン太陽電池モジュールでは、近紫外光領域の感度がとても低いことが問題となっています。当研究室では、近紫外線を可視光や近赤外線に変換する蛍光体を太陽電池に組み合わせて光電変換効率を向上させることを検討しています。太陽電池上部に蛍光体層を導入する場合、感度の高い可視光を透過する蛍光体層、つまり見た目には透明に見える蛍光体層が求められます。
紙幣、パスポート、クレジットカードなど身近にあるものには、見た目にはわからないように蛍光体が塗られています。これは、偽造防止などのセキュリティーを目的として蛍光体が応用された例です。そのほかに、飲料用の缶、配達される郵便物などにも見た目にはわからないように蛍光による識別コートが印刷されています。ブラックライト(UVランプ)を使って、いろいろなものに紫外線を当てると上記の例に気がつきます。
炭素材料は、原料が豊富にあることから、とても注目されています。当研究室では、ナノサイズのカーボン(カーボンドット)を作製することを研究しています。このカーボンドットは、多くの場合は、紫外線を吸収し、青色に光ります。しかし、最近は、緑色や赤色に光るカーボンドットも発見されています。カーボンドットは、LEDの波長変換材料、バイオイメージングの蛍光プローブや、特定の金属イオンのセンシングなどに応用できることが報告されていますが、まだ未解明なことが多い材料です。
研究材料
材料の形態は、ナノドット(球状ナノ粒子)、ナノシート、コア/シェル、コンポジット(複合材料、例えば高分子とドットとの複合や、ドットとナノシートとの複合)などを取り扱っています。発光の効率を高めるために、ナノドットの微細構造をコア/シェル構造にする方法や、ナノドット表面の修飾分子を設計することを検討しています。また、ナノ材料は周囲の環境の影響を受けて劣化しやすいため、発光の安定性を高めることも検討しています。
研究材料は、下記の4つに大きく分類できます。
- 量子ドット コア/シェル型 CuInS2/ZnS, CuGaS2/ZnS など
- ペロブスカイト量子ドット CsPbX3 (X = Cl, Br, I) など
- 鉛フリー量子ドット
- カーボンドット(グラフェン量子ドット)
ひとりひとりが全員異なる研究テーマに取り組んでいますが、それぞれ少しずつ関連する部分を含みますから、お互いに協力し合いながら研究を進めています。これまでの研究テーマに関しては研究紹介ビデオを参考にしてください。
研究室が求める人材
- 最先端の蛍光体材料やナノ材料を研究開発したいという高いモチベーションを持つ人
- 大学院に進学して3年間以上意欲的に研究に取り組み国際的に有名なジャーナルへの論文発表にチャレンジしたい人
実験を集中して、そして、安全に行うために、健康的に生活することは不可欠です。そして、毎日、実験を少しずつ地道に積み上げていくことが大切です。
上述のような研究テーマを取り扱っていますので、当研究室へ配属を希望する方は、無機化学・物理化学の基礎をマスターし、磯部が担当するマテリアルデザイン概論2をはじめとするマテリアルにかかわる科目を履修し、とくに発光材料に興味を持っている方に適しています。
研究室の魅力
研究室では、頻繁にディスカッションし、学会発表や学会予稿・学術論文の執筆に関して非常にていねいな研究指導を行っています。そして、達成感のある研究活動を行えるように、修士課程修了までに次のような目標を目指しています。
国内学会発表 複数回
国際学会発表 1回以上
筆頭著者としての学術論文発表 1編
実際に、ほとんどの学生がこの目標を達成できています。
研究室の環境
学生の皆さん方が安全・安心して研究室で過ごすことができるように、居室と実験室は完全に分かれた環境になっております。メンバー構成は、つぎのように推移しています。
(2018年度)博士1年 1人、修士2年 4人、修士1年 5人、学部4年 6人、大学院協定研究生 2人
(2019年度)博士2年 1人、修士2年 5人、修士1年 4人、学部4年 6人
(2020年度)博士3年 1人、修士2年 4人、修士1年 2人、学部4年 7人
(2021年度)修士2年 2人、修士1年 4人、学部4年 7人、大学院協定研究生 1人
(2022年度)修士2年 4人、修士1年 3人、学部4年 6人、大学院協定研究生 1人
(2023年度)博士1年 1人、修士2年 3人、修士1年 1人、学部4年 7人
(2024年度)博士2年 1人、博士1年 1人、修士2年 1人、修士1年 3人、学部4年 7人、大学院協定研究生 2人
(2025年度)博士3年 1人、博士2年 1人、修士2年 3人、修士1年 7人、学部4年 7人、大学院協定研究生 2人
(2026年度予定)博士3年 1人、修士2年 7人、修士1年 6人、学部4年 7人
実験室は整理整頓され、研究設備もたいへんよく整っています。ナノ粒子を合成するための耐圧反応装置、ナノ粒子の大きさ・比表面積を測定する装置、結晶構造を評価する装置、ナノ粒子表面に吸着した有機物を分析する装置、ナノ粒子の光吸収・蛍光特性を評価する装置、太陽電池やLEDの特性を評価する装置などが用意されています。恵まれた研究環境であることは、研究室の見学やウェブメニューの研究室ツアーをご覧いただくとおわかりになると思います。このような環境が整備できた理由は、研究室の研究成果が認められ、多くの機関が研究を支援して下さったためです。また、透過型・走査型電子顕微鏡、ラマン分光、電子スピン共鳴などの大型の分析装置は、中央試験所で予約して利用することが可能です。
研究スキルの向上を目指して
研究室で充実した生活を過ごし、ある程度まとまった研究成果を達成するためには、修士課程へ進学することをお勧めしております。とくに、メーカーの技術職へ就職することを希望される場合は、修士課程を修了することが必須と考えた方がよいと思います。コンサルタント、金融、総合商社などの文系就職においても研究に従事した経験が評価されます。外資系では修士の学位がアピールポイントになります。
就職して行う仕事は、研究室の研究と直接関係があることはまれです。このため、研究室では将来にわたって役立つ基礎を身についてほしいと願っています。したがって、研究のスキルを磨くことも大切です。一方、自分の考えていることを相手に伝える作文能力・プレゼン能力を磨くことに力を入れています。そして、グローバルな活動に必須である英語でのコミュニケーションにも力を入れています。修士課程修了までに、国際学会での発表、英語での論文執筆を目指して指導しています。
研究室の志望理由書の書き方
与えられた紙面は、十分に活用して自分自身をアピールしてください。つぎのような項目に分けて、わかりやすく、読みやすく、魅力的な理由書を、よく練って作ってみてください。なお、手書きで書く必要はありません。
- 勉学のあゆみ: 大学入学後に力を入れて勉強した分野(必修科目だけでなく、どのような選択科目を履修し、勉強し、興味をもったか? 応用化学科パンフレットの履修科目の系統図を意識して、マテリアル関連の科目を選択したか? など)→ 研究室選択のミスマッチをなくしたい!ベースになる知識がないと研究できません!
- 志望理由: 当研究室を第1希望として選んだ理由(①を踏まえて研究室を選択したか? 上記の「研究室が求める人材」と合致するか? 研究室を事前に見学したか? 見学してどのような印象を持ったか? 応化懇親会などで個別に話をしたか? など)
- 希望研究テーマ: 卒業研究でどのような研究に取り組みたいか?(研究室見学・説明会での話を聞いて、あるいは、ホームページやYouTubeの動画を見て、どのような研究に興味を持っているか?)ただし、公開している情報は最新ではないので、希望の通りテーマが設定されないこともあります。
- 今後の進路: 将来、研究者・技術者を目指してどのような進路を考えているか? 大学院まで進学して自分の研究テーマをどのように発展させていきたいか? など
磯部教授の経歴
磯部教授は、米国とフランスでそれぞれ1年間の訪問研究員としての留学経験を持っています。米国・テネシー州のナシュビルではVanderbilt大学およびOak Ridge National Laboratoryでシリカガラスへニッケルイオンを加速して注入した材料に関する研究を行いました。フランス・パリではESPCI (Ecole Superieure de Physique et de Chimie Industrielles de la Ville de Paris)でアパタイトナノ粒子およびアモルファス水酸化アルミニウムを固体核磁気共鳴分析によって解析する研究を行いました。現在の研究とはかなり異なる経験を積んで広角的な視野で研究を進めています。また、フランスへはその後3名の学生さんを派遣することができました。一方、フランスから8名の学生さんを協定研究生として受け入れました。
磯部教授は、日本の蛍光体分野を先導する「蛍光体同学会」において、長年、幹事を務め、現在は会長として講演会の企画・運営に貢献しています。また、磯部教授は、これまで下記の4冊の蛍光体の書籍を監修者として取りまとめています。いずれも、理工学メディアセンターに所蔵されています。
- 「ナノ蛍光体の開発と応用」(2007年8月発行)(さらに普及版が2012年11月発行)
- 「波長変換用蛍光体材料 -白色LED・太陽電池への応用を中心として-」(2012年8月発行)(さらに普及版が2019年3月発行)
- 「次世代蛍光体材料の開発」(2016年7月発行)(さらに普及版が2023年3月発行)
- 「<続>次世代蛍光体材料の開発」(2024年8月発行)
卒業生の進路
ソニー・パナソニック・日立製作所・コニカミノルタ・東芝・リコー・富士ゼロックス・スタンレー電気・ルネサステクノロジ・トヨタ自動車・豊田自動織機・日本ペイント・関西ペイント・大日本印刷・東京ガス・大陽日酸・三菱マテリアル・京セラ・村田製作所・日本化薬・JT・日清エンジニアリング・クボタ・JX日鉱日石エネルギー・住友化学・AGC・古河機械金属・東京応化工業・フジクラ・日揮・IHI・日本ユニシス・カシオ計算機・日本技術貿易・東北大学・産業技術総合研究所など
磯部研究室の学生の活躍
学会での受賞
水平方向にスクロールできます。
| 2025年10月 | 丸山 蒼生 君 | 「第15回CSJ化学フェスタ 優秀ポスター発表賞」 |
| 2025年10月 | 中林 杏実 君 | 「第15回CSJ化学フェスタ 優秀ポスター発表賞」 |
| 2025年10月 | 今村 麻保 君 | 「第15回CSJ化学フェスタ 優秀ポスター発表賞」 |
| 2025年9月 | 子安 弘樹 君 | 「日本セラミックス協会第38回秋季シンポジウム 優秀発表賞」 |
| 2024年9月 | 今給黎 祐 君 | 「日本セラミックス協会第37回秋季シンポジウム 優秀発表賞」 |
| 2022年10月 | 片上 凜香 君 | 「第12回CSJ化学フェスタ 優秀ポスター発表賞」 |
| 2022年8月 | Rika Katakami | 「Best Poster Presentation Award: The 12th International Symposium for Luminescent Materials Phosphor Safari 2022」 |
| 2019年11月 | Kazuhiro Taki | 「Poster Award: 11th International Symposium on Luminescent Materials Phosphor Safari 2019」 |
| 2019年11月 | Rina Sato | 「Poster Award: 11th International Symposium on Luminescent Materials Phosphor Safari 2019」 |
| 2018年11月 | Shimpei Miyata | 「Award (Competition for the best presentation: The 1st Prize Winner): International Symposium for Luminescence Materials & Applications Phosphor Safari 2018」 |
| 2017年12月 | Taichi Watanabe, Yoshiki Iso, Tetsuhiko Isobe, Hirokazu Sasaki |
「Outstanding Poster Paper Award: The 24th International Display Workshops(IDW'17)」 |
| 2015年7月 | Kohei Yano | 「Phosphor Safari 2015 Best Poster Award: International Symposium on Phosphor Materials 2015」 |
| 2011年9月 | 磯 由樹 君 | 「第24回日本セラミックス協会秋季シンポジウム 研究奨励賞」 |
| 2010年11月 | Kenji Akisada, Yusuke Noguchi, Tetsuhiko Isobe | 「The Poster Award: The 3rd International Congress on Ceramics (ICC3) Symposim 5 "Hybrid and Nano-Structured Materials」 |
| 2010年3月 | 竹下 覚 君 | 「第27回応用物理学会 講演奨励賞」 |
| 2008年5月 | 朝倉 亮 君 | 「日本分子イメージング学会 優秀発表賞」 |
| 2007年9月 | 草山 育実 君 | 「第22回応用物理学会 講演奨励賞」 |
| 2006年9月 | Wakana Kichikawa, Fumiaki Nishimura, Tetsuhiko Isobe | 「Best Paper Award: The International Union Materials Research Society - International Conference in Asia 2006 (IUMRS-ICA 2006)」 |
慶應義塾および関連団体からの受賞
水平方向にスクロールできます。
| 2021年3月 | 佐藤 康平 君 | マテリアルデザイン科学専修 機能創造賞 |
| 2021年3月 | 慶長 泰周 君 | 総合デザイン工学専攻 優秀研究活動賞(博士) |
| 2019年3月 | 佐藤 康平 君 | 一般財団法人慶応工学会 慶応工学会賞 |
| 2016年3月 | 慶長 泰周 君 | 理工学部/理工学研究科 藤原奨学基金運営委員会 藤原賞 |
| 2015年3月 | 磯 由樹 君 | 総合デザイン工学専攻 優秀研究活動賞(博士) |
| 2011年3月 | 竹下 覚 君 | 総合デザイン工学専攻 優秀研究活動賞(博士) |
| 2010年2月 | 竹下 覚 君 | 理工学研究科 国際会議論文発表奨励賞 |
| 2009年3月 | 竹下 覚 君 | 総合デザイン工学専攻 優秀研究活動賞(修士) |
| 2008年3月 | 粕谷 亮 君 | 総合デザイン工学専攻 優秀研究活動賞(博士) |
| 2007年7月 | 朝倉 亮 君 | 理工学研究科 国際会議論文発表奨励賞 |
| 2007年3月 | 竹下 覚 君 | 慶應義塾大学 義塾賞(表彰学生) |
| 2007年3月 | 草山 育実 君 | 応用化学科 慶應応化進歩賞 |
| 2005年12月 | 粕谷 亮 君 | 理工学研究科 国際会議論文発表奨励賞 |
| 2005年6月 | 粕谷 亮 君 | 理工学研究科 国際会議論文発表奨励賞 |
| 2004年3月 | 三木 拓朗 君 | 機能創造理工学専修 機能創造賞 |
博士号取得
将来、一人前の研究者になり、グローバルに活躍したいという高い志をお持ちの方は、当研究室で博士号を是非取得してほしいと願っています。当研究室で博士課程へ進学した方の多くは、日本学術振興会の特別研究員などに採用され、経済的なサポートを受けながら、研究に専念できています。
過去の採用実績
水平方向にスクロールできます。
| 2020年4月~2021年3月 | 慶長 泰周 君 | 日本学術振興会特別研究員(DC2) |
| 2019年4月~2020年3月 | 慶長 泰周 君 | 慶應義塾大学大学院理工学研究科 助教(有期・研究奨励) |
| 2014年4月~2015年3月 | 磯 由樹 君 | 日本学術振興会特別研究員(DC2) |
| 2013年4月~2014年3月 | 磯 由樹 君 | 慶應義塾大学大学院理工学研究科 助教(有期・研究奨励) |
| 2011年4月~2012年3月 | 竹下 覚 君 | 日本学術振興会特別研究員(PD) |
| 2009年4月~2011年3月 | 竹下 覚 君 | 日本学術振興会特別研究員(DC1) |
| 2008年4月~2009年3月 | 朝倉 亮 君 | 日本学術振興会特別研究員(DC2) |
| 2006年4月~2008年3月 | 粕谷 亮 君 | 日本学術振興会特別研究員(DC1) |